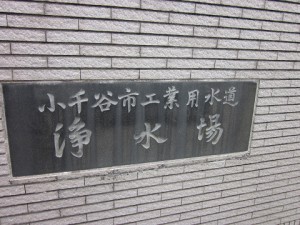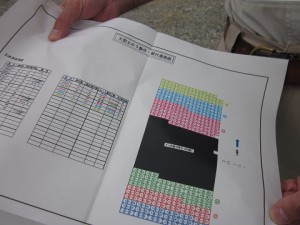6月定例会の一般質問終了しました。
病院統合問題は、私を含め、2名の議員が質問したのですが、結局、今回も、同じ市長答弁。
「進捗しているが、お話できることはない。」
近隣市町村で病院整備が進んでいる中で、非常に不安です。
いろいろ頭を整理して、再質問など、一般質問のまとめは、明日の夜に、掲載します。
(長谷川あり:一般質問)
私は、先に通告いたしました2項目について質問致します。
まず、一項目目として、21世紀の小千谷の未来投資と人材育成の課題について質問致します。
超高速化する少子高齢化や日本経済の混迷の中で、低成長下での税収の低下、社会保障関連経費の増大は、必至であり、合わせて地域間競争の時代にあって、当小千谷市も生き残りをかけ、第4次小千谷総合計画後期基本計画の方針に基づき、順次進めておる所でありますが、小千谷の若者として、21世紀の小千谷の未来投資と人材育成を当市はどのように、進めようと考えているのか、端的にお答えをお聞かせ下さい。
まず、1点目ですが、当市は中越大震災以降、長岡市、旧山古志村・旧川口町、旧小国町等の近隣市町村と、震災直後より連携協力して広域行政としての支え合いを進めてきたところであります。
中越大震災最大の課題は、中山間地の再生復興でした。小千谷市においても、東山地域、南部地域、山辺地域等での厳しい現実は学校の統廃合にも象徴されています。21世紀小千谷の生き残りには、中山間地が元気で、魅力をアピールできる存在でなくてはなりません。そのための交流が多く生まれています。
そうした活動の1つとして、財団法人山の暮らし再生機構、通称LIMOがあります。財団法人山の暮らし再生機構に、小千谷市長は、顧問として、また、評議員として、小千谷市のNPO法人理事長の方が名前を連ねております。
また、先日、新聞報道された新潟県が社団法人中越防災安全推進機構に委託し、行う「中越・山の暮らしインターンシッププログラム」に、山の暮らし再生機構も協力しており、当市の農園ビギン、わかとち未来会議、農事組合法人うちがまき絆も、インターンシップの受け入れ先として、参加を表明されております。
しかし、山の暮らし再生機構の地域復興支援センターに小千谷市は入っていません。長岡センター(太田東山担当、小国サテライト、山古志サテライト、栃尾サテライト、川口サテライト)、南魚沼センター、十日町センターはありますが、小千谷センターはありません。
また、年4回発行の広報誌LIMO通信は、平成24年3月30日号が最新号ですが、そちらにも、小千谷市の情報は載っていません。
中越地域の広域連携として中山間地の復興を目指した財団法人山の暮らし再生機構に、なぜ、当市は参加していないのかお聞かせ下さい
2点目として、防災ラジオについてお伺いします。平成24年度の小千谷市予算の目玉でもある防災ラジオ(緊急告知ラジオ)の全世帯・全事業所への無償配置ですが、5月15日の小千谷市議会の第一回臨時会でも、長岡市・出雲崎市・見附市も含む配信エリアをもつFMながおかの電波を使うことで、「小千谷市内だけ」とか「小千谷市内の特定の地区だけ」に緊急放送を流すといったことに対応できない実態に、1台約1万円、合計1億6200万円もかけて、導入する意味があるのか、私も含め、多くの議員からも疑問の声が出されました。
また、平成23年度中に試験配置として、町内会長や消防団員、民生児童委員にラジオが配布されていた中で、先日の池ヶ原の地滑りでは緊急告知ラジオは使用されず、携帯の災害メールは周知されたなどの実態がわかり、どの災害レベルから、情報を告知するのかなど、4月、5月と市内で開催された「市民と市長の懇談会」でも、多くの質問が市民の方から、寄せられていました。
臨時会での市長の説明でも感じましたが、そもそも防災ラジオの役割を万能薬のようなものとして、市民が誤解してしまうように、告知されてしまったのではないでしょうか。防災行政無線を新設・増設するよりもコストがかからないという理由が背景にはある中、緊急告知ラジオの素晴らしさだけが過剰に宣伝されてしまったのではないかと感じています。
例えば、「熊本市緊急告知ラジオ」を有償配布している熊本市では、昨年6月の大雨で、土砂災害の危険性から避難情報を発令し、その経験から、2011年9月号の市政だよりで、「災害に備えて~避難情報を学ぶ~」の特集ページで、避難情報の種類とともに、災害情報メールの読み解き方に写真を使って、大きく画面をさいて説明しております。
また、その中で、「避難情報が発令されると次の方法で、みなさんにお知らせします。自ら判断して早めの避難を心がけて下さい。」として、告知方法として、①広報車や消防団による周知、②市ホームページへの掲載、③市災害情報メールによるメール通知、④緊急告知ラジオなどによる放送、⑤テレビ・ラジオなどの報道機関からの放送の5つを挙げております。
このように、緊急告知ラジオを特化して扱っておりません。
障がい者など災害時要援護者の方にとっての防災避難における情報伝達はどうあるべきなのかも含め、実際に、台風や大雨が懸念されるこの時期、市民にとって、災害時の様々な情報や避難情報をどう読み解いて、判断して、自らの安全を守り、地域の安全を守れるのか、防災ラジオで事足りることではなく、市民に対して、丁寧な説明が必要と考えますが、市長の見解をお聞かせ下さい。
3点目として、行政改革委員会の委員選出方法、また行政改革委員会に市長が期待することについて伺います。
日本の現状に閉塞感が二重にも三重にも渦巻く中、既存政党への支持が低迷する中で、全てが支持出来るわけではないですが、大阪維新の会を率いる橋本大阪市長に、既得権益の打破、民間活力、市民力の活用を夢見て、期待を寄せる傾向がかなり強まっている現状にもあらわれているように、行政改革に対する市民の目はかなり厳しいものがあります。
市民と市長の懇談会でも、行政改革に対して、厳しい意見が市民の方から出されております。
小千谷市においては、平成21年12月改定の行政改革大綱に基づき策定した行政改革実施計画の期間は、平成22年度から平成24年度までの3年間であり、次期の行政改革実施計画の策定に入るにあたり、21世紀の中長期展望を指し示すものにしていかなければなりません。
市役所、議会も含め、オープンに行政大改革を考えていくべきです。
選出された行政改革委員会の委員の中に、東京電力の社員の方や市役所OBの方が、選ばれている委員会に、市民は期待できるのでしょうか。市長の見解をお聞かせ下さい。
4点目として、ふるさと納税の昨年度の実績と、5点目として、クラインガルテンの入居率が春から向上したのか、お聞かせ下さい。
6点目として、三洋半導体岐阜、群馬工場の小千谷工場の集約移動の進展状況をお聞かせ下さい。小千谷市定住促進支援事業も立ち上げてきたところですが、2010年9月の新聞各紙で、2012年をめどに、両工場の閉鎖を進め、小千谷市の新潟工場へ生産を集約する方針が、報道されており、市長が再選された市長選でも、このことが盛んに喧伝され、市民も大変期待しておりました。現状をお聞かせ下さい。
7点目として、選挙における投票所の集約等の改善に向けた住民の意向調査が先般の町内会長会議で公表されたとのことですが、公民館分館活動の「明るい選挙推進協議会」の解散、市選管移管なども報告されています。個人演説会さえ出来ない不公正な公民館等を使用した選挙事務所のあり方なども含めて、検討されるべきと考えますが、見解をお伺いします。
8点目として、相互に多くの成果がある国・県との人事交流を進めるべき
と考えますが、予定はあるのか、市長の見解を伺います。また、小千谷市の人事異動の内示の概要における「人事異動の考え方」等の記述をみても、女性職員の管理監督職登用の推進等での具体的な数値を明記している他市の内示と比較しても、人材育成・投資に関する市長の戦略的方針やリーダーシップをあまり感じられません。
あまり他市との比較はしたくないのですが、「十日町市の人事異動内示」という文書があります。毎年、十日町市のホームページに掲載されていて、誰でも見ることができますが、平成24年3月14日付のモノでは、平成24年は定員適正化の推進、女性職員の管理監督職登用の推進がきちんと目的も含めて、記載されています。また、平成23年には、「国本省への職員の派遣として、高い政策形成能力等を有する職員を育成するため、新たに経済産業省並びに環境省の本省に職員を派遣する。」と明記されています。これに対して、小千谷市の「人事異動内示の概要」、これは、総務課から提出してもらったものですが、人事異動の考え方は、事実の羅列で、なぜそれを行うのかの目的も記載されていない、市長の強い意思を感じない味気ないものです。
中長期的視野を持った戦略的な人材育成は、21世紀小千谷の未来投資に欠かせないものです。市長の見解をお聞かせ下さい。
9点目として、市が実施したパブリックコメント募集に対し、集まった意見が極端に少ないと考えますが、市長の見解をお聞かせ下さい。
最近のパブリックコメントへの意見数の状況としては、2011年12月12日から26日まで意見募集された「小千谷市歯科保健計画(案)」に対しては、意見4件、2012年2月1日から10日に意見募集された「第9次小千谷市交通安全計画(案)」については、意見0件、同じく、2012年2月1日から10日に意見募集された「第3次おぢや男女共同参画プラン(案)」も0件、2012年1月25日~2月6日に意見募集された「小千谷市高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画(素案)」に対しては、意見1件、2012年2月25日~3月9日まで意見募集された「小千谷市障がい者計画(案)」に対しては、意見10件と非常に、少ない件数であります。
交通安全計画と男女共同参画プラン、ともに意見0件ですが、意見を募集したのが、2月という市民が一番豪雪で大変な労苦にあえいでいた時期ということもあります。
募集の時期や方法の見直しも含め、市長の見解をお聞かせ下さい。
次に、二項目目として、病院統合と住みよいまち小千谷を守る展望についてお聞きします。午前中の田中議員の質問と重複する質問も多いかと思いますが、ご容赦ください。
1点目として、市長は公約で、両病院統合をうたわれていますが、市長も記者発表された平成25年4月までの統合は実現するのでしょうか
2点目として、市議会や市民にも、病院統合の内実が知らされていない中で、財政支援を決定されているような発言が、一般質問の答弁でも、市民と市長の懇談会の片貝会場においても、しばしば市長から発言がありますが、小千谷の医療の現状と未来のあるべき姿に対して説明もない中で、財政支援のお話が簡単になされていることに市民は納得するのでしょうか。市民に対して説明責任はないのでしょうか、見解をお聞かせ下さい。
3点目として、県立十日町病院の新築は、平成25年度までの着工、魚沼市新病院は、平成24年実施設計、平成25年度建設工事、平成27年開院予定、魚沼基幹病院が平成27年開院予定と近隣市町村では病院統合が進み、ますます医師と看護師の確保が懸念される現状があります。小千谷市の新病院では、どう医師と看護師を確保するのか、市長の見解をお聞かせ下さい。
4点目として、病院統合の進捗に伴い、市民に対する丁寧な説明が必要であると考えますが、魚沼市では「これからの魚沼地域の医療」という出前講座を行い、魚沼地域の医療の現状を説明しています。今後、「出前講座」や「新病院や小千谷の医療に対する市民から意見を聞く会」等を開催・開設する予定はないのでしょうか。市長の見解をお聞かせ下さい。
5点目として、病院統合の進捗に伴い、地元住民・地元医師会・学識経験者・議会・病院関係者を含めた地域医療整備協議会などを開催する必要があると考えますが、見解をお聞かせ下さい。
以上で、質問を終わりますが、答弁のいかんにより、再質問させていただきます。