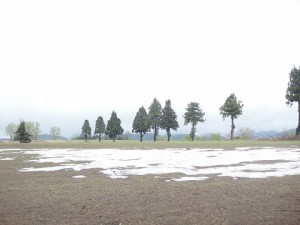極楽パンチ
5月 20th, 2012 by hasegawa小千谷市消費者協会設立30周年
5月 18th, 2012 by hasegawa緊急告知ラジオ
5月 15th, 2012 by hasegawa質疑が集中したのは、緊急告知ラジオについて。
平成24年度の小千谷市予算の目玉でもある防災ラジオ(緊急告知ラジオ)の全世帯・事業所等への無償配置。
平成23年度中に試験配置として、町内会長や消防団員、民生児童委員、公共施設などに配置されていますが、ここにきて、先日の池ヶ原の地滑りなどでは告知されないなどの実態がわかり、どの災害レベルから、情報を告知するのか?また、長岡市・出雲崎市・見附市も含む配信エリアをもつFMながおかの電波を使うことで、「小千谷市内だけ」とか「小千谷市内の特定の地区だけ」に緊急放送を流すといったことに対応できない実態に、1億3650万円もかけて、導入する意味があるのか、私も含め、多くの議員からも疑問の声が出されました。
また今回3件の財産取得の議案が提出されましたが、緊急告知ラジオを含め、2件は「随意契約」による取得。意見を付しての賛成討論を行いました。
県内の他自治体でも導入されている緊急告知ラジオですが、疑問点や納得いかない点も多く、今後も調査・研究を行ってまいります。先日の町内会長会議や「市民と市長の懇談会」でも、多くの質問が寄せられています。市民の皆さんからも意見をお寄せください。
「私は、議案第49号、第51号に対し、意見を付して賛成の討論を行います。位置情報通知システム一式の取得に、2,058万円、緊急告知ラジオの取得に、1億3,650万円と、いづれも、随意契約による取得であります。高額な財産取得に対し、随意契約を行う説明がなく、随意契約で、市民の血税が使用されることに、一抹の危惧や不安を感じざるを得ません。日本は「競争入札主義」による契約を定めています。随意契約 は、その例外として行われなければなりません。国や地方公共団体が随意契約 を結ぶことができる例としては、少額の契約をするとき、特定の者でなければ納入することができない製品を購入するとき、それに代わるものがない土地などを購入するとき、緊急のときなどがあげられております。先ほどの質問では、今回の随意契約は、特定の者でなければ納入することができない製品を購入するという条件に該当するという答弁でしたが、少しでも、市民に、無競争のための税金の無駄遣いや談合、業者の選定の不透明さ、業者と癒着しやすいための汚職の温床などの不信感を与えることは慎まなければなりません。
「李下に冠を正さず」といいます。公平性や透明性の確保とその説明責任を切に願います。
今後、随意契約により、財産の取得を行う際には、内容を透明化し、なぜ随意契約が必要なのかということをはっきりさせ、説明責任を果たせるようにしていただきたい。市民が納めた税金をできるだけ節約して有効に使うこと・公正さや機会均等の確保を行うためにも、小千谷市は、具体的な随意契約の内容・理由等を公表し、自らを律していこうという姿勢を示していただきたい。議案49号、第51号に対しては、以上の意見を付した上で、賛成といたします。」
ちなみに議案第49号の位置情報通知システムは、富士通ゼネラルとの随意契約。
固定電話の位置通報通知システム導入時に、沖電気・富士通・NEC・松下の競争入札の予定が、小千谷消防署のスペースの制約があり、沖電気と富士通の2社の指名競争入札になり、富士通に決定した背景があり、今回の携帯電話の位置情報通知システムを導入する際も基本システムが富士通ゼネラルなので、富士通との随意契約になったとの市の説明。
第51号議案の緊急告知ラジオは、FMながおかのみを受信するラジオで、脇屋技研(社長はFMながおか社長)のみ製造できるラジオとのこと。そのラジオを購入するにあたり、市内の経済活性化のために、新潟県電機商業組合小千谷支部(16社)との随意契約になったとの市の説明。ラジオ(コムフィスR-1)は本体1台7,700円、設置にかかる諸経費が1台2,200円で、1台9,900円で取得とのこと。
城内高砂会
5月 14th, 2012 by hasegawa

 5月11日(金)城内町の高砂会合同総会にお邪魔しました。
5月11日(金)城内町の高砂会合同総会にお邪魔しました。
城内町はいわゆる老人会として第1高砂会から第3高砂会まで会があるのですが、総会後の懇親会で、皆さん和気あいあいとした雰囲気で楽しんでいらっしゃいました。
小千谷市の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は、平成23年27.6%から、ついに平成26年には、30.2%と、30パーセントを超えると予想されています。(特別養護老人ホームの入所申込者数(平成23年8月1日現在)いわゆる待機者数は364人で、うち在宅の方で要介護4~5の重度者は72人とされています。)
変化し続ける社会、地域、家族、意識、そして制度の中で、身の回りに増える医療依存度の高い人たち、自己決定や契約の難しい人、手助けや介護の必要な人、さらには、独居、老老介護、孤独な子育ての課題が浮かび上がっています。
多くの人が失った人と人とのつながりの再生、そこから生まれる安心社会の再構築を望んでいるのが現状です。
しかし、ただの懐古主義では、問題解決は難しい。全国各地で、試行錯誤の様々な取り組みが行われています。
誰でも、参加できる「居場所」をつくること、その地味な取り組みを継続することで大きな光が見えてくる・・・
そのような認識の中、城内町内会様や高砂会様のお力添えで、城内に、「地域のお茶の間・城内」が誕生しました。
助け合いの仕組みを作り、今は、たまたま手助けできるが、いつか必ず手助けをうける時が来る。また、この世の中に、世話になるばっかりの人はいない。皆、出来ることがある。ここがあって良かった!今できることをしよう!という人の心をつなげていく。
そんな想いが「地域のお茶の間・城内」であり、地域交流・お互い様の地域の絆づくり「ボランティア城内」につながっています。
こころのつながる、ほっとする場、それが「お茶の間」。(全国でも爆発的に増えてます)
その効用は・・・
1.人と人とのつながり、人と、社会とのつながりをつくる。
2.知り合うことで、人の不自由を知り、人へのやさしさが育ち、地域に広がる。
3.いざ!という時、困ったときに気軽に助け合える人間関係が生まれる。
4.お互い様の関係を作り、地域に暮らし続けられる安心感を育てる。
5.地域住民が、自らのために力(人手・物・知恵・金)を出し合う。
6.視野の広いこどもに育つ、地域の人から見守られる安心感、子育て中の親の孤独、不安、拘束間の解消
7.異世代、異文化の交流から、伝統、文化の伝承(その地に伝わる料理、習わし、作法、気遣い、生活の知恵・・・)
8.情報の共有化が一度にできる(防犯、防災、健康相談、新しい制度・・・)
市民の声
5月 11th, 2012 by hasegawa5月の連休も終わり、いよいよ小千谷でも、田植えが始まる田んぼも出始めました!
4月から、「市民と市長の懇談会」が市内各地で開催されていますが、私もなるべく参加して、市民の皆さんの声を聞きたいと4月20日の川井・岩沢地区、4月25日の真人(里地)地区、5月9日の千田高梨地区の懇談会に出席しました。
雪害や病院統合問題が一番質問として多いのではと思っていたのですが、どの会場でも震災がれきやヨウ素配備の質問が住民の方から一番に質問されていました。
「岩沢田代では、産業廃棄物処分場が問題となってきている歴史がある。震災がれきは受けれないでほしい。」
「柏崎刈羽の30キロ圏内に小千谷は入る。特に冬はもろに風の影響を受ける。脱原発の声を首長として出してほしい。」
「ヨウ素はどう配備するのか。」
「小千谷は原発の30キロ圏内に入る。町内の女性たちも気にしている。来迎寺まではヨウ素を配っていると聞いたことがあるが、小千谷はどうするのか?」などなど。
上記の質問に、市長の答えは、※小千谷市は、震災がれきは受け入れない。(市内のゴミの最終処分を県外にお願いしているが、受け入れ先から、震災がれきの灰は受け入れないと言われている)※ヨウ素の配備は国の指導で対応したい。とのことでした。
原発の問題(福島第一原発事故・柏崎刈羽原発)は私自身も重要な課題であるとの認識で、昨年も議会で多く取り上げてきましたが、市民の皆さんの関心も高いです。
不安、疑問にしっかりと応えていかなくてはなりません。
情緒的な安全神話で取り返しのつかなることが発生した場合は、誰が責任をとれるのでしょう。
泉田知事も、先日のBSフジの番組で、「神話なき安全を!」と訴えていました。
きちんとした科学的な議論を積み重ねる努力をしたいものです。
今後、「市民と市長の懇談会」は、5月16日東小千谷地区(勤労青少年ホーム)、5月19日西小千谷地区(サンプラザ)、5月24日山辺・吉谷地区(吉谷トレセン)、5月31日片貝地区(片貝総合センター)で19時30分から21時の予定で開催されます。
是非、大勢の市民の皆さんのご参加を!
山本山スローライフ菜の花圃場
5月 5th, 2012 by hasegawaちまきづくり
5月 4th, 2012 by hasegawa
 明日は、端午の節句ということで、デイサービスセンターほのぼのでは、ちまきづくりをしました。
明日は、端午の節句ということで、デイサービスセンターほのぼのでは、ちまきづくりをしました。
小千谷では、笹の新しい葉が出る頃が、ちまきや笹団子を作る時期なので、一か月ほど早いのですが…。
笹の葉の新鮮な香りの中で、もち米をつめて、笹でくるんで、すげで巻きました。
一時間ほど茹でた後、干します。今日、作った分は、明日、デイサービス・グループホームの利用者さんと食べます。
今日作成していただいたデイサービスの利用者さんには、昨日グループホームで作成し、干していたちまきを食べていただきました。
それこそ、時季には、何十個(何百個?)とちまきや笹団子を作って、親類や知人に送っていたという地域柄。
利用者の皆さん、「つくったの、何年ぶりだ~」「もう、覚えてないて~」と言いながら、しっかり、手つきはプロでした。
若い介護士も興味津津。地域の伝統食を皆で作ることも楽しいですね。
毎年、この時期に、私も、ホームで、ちまき作りを手伝いますが、いつも、一から教えてもらうことに。(今年は、覚えられたかな?)
笹の葉が出てきたら、笹取りにも行きたいね~と利用者さん達も話がはずんでいました。
祝!成人
5月 3rd, 2012 by hasegawa小千谷は、本日5月3日が成人式でした。
式の開始前には、ちょうど雨もあがり、スーツや着物・袴姿の成人の皆さん、一人一人が輝いていました。
ただ、成人の皆さんの素敵な姿、式だけではちょっともったいない感じがしました。
十日町市では成人式と十日町きものまつりが同日開催されるように、街が着物姿で彩られる黄金週間の1日があってもいいですよね。
写真は、市民憲章 小千谷市民のねがい を 読み上げる新成人の皆さん です。
美しい山河にめぐまれ、深い雪におおわれる この風土に生きた先人は、やさしく忍耐強い気風と、おおらかな雪国の文化と、独創的な産業を育ててきました。これをうけつぐわたくしたち市民は、次の目標をかかげ、さらに光ある明日をめざして進みます。みんなで「わがまち小千谷」を育てましょう。
雪にくじけぬ、たくましいまちに。いたわりと真心のあふれるまちに。健康で、文化の香り豊かなまちに。はたらく喜びにみちた産業のまちに。
(昭和55年3月1日制定)
知事との意見交換
5月 2nd, 2012 by hasegawa本日は新潟県庁へ。
泉田知事と新潟の若市議会の議員(全国若手市議会議員の会北信越ブロック新潟県地区の議員)の懇談会に参加しました。
震災がれき問題から、新潟州構想、教育、揚水発電など、様々な分野について意見交換がされました。
私は、「地域医療」について。
基幹病院や急性期の病院とのすみ分けの中で、どうすれば、地域の通常医療や慢性期の病院での医師を確保できるのかについて、見解を伺いました。
知事の回答は、「医学部の新設!」とのこと。
小千谷でも総合病院の統合が期待されますが遅々として進まない現状、それにひきかえ、着々と進む魚沼基幹病院構想の中では、たとえ、何年後に小千谷において統合病院の箱物が出来たとしても、勤務する医師を確保できるのか、不安です。
医師の東京集中や西高東低の傾向の中では、新潟県における医学部の新設は待ち望まれます。
実際、在宅医療を国は推進していく方針ですが、在宅医療を支援する病院・診療所は、厚労省のデータでも、新潟県は少なく、西日本や北陸が高い数値が出ています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_a-5.pdf
厚労省 平成24年3月30日厚生労働省医政局長通知 医療計画について 資料Aー5 :在宅医療について 18頁・19頁
自治体議員女性政策研究交流会
4月 29th, 2012 by hasegawa池ヶ原町内の一部6世帯15人に出されていた避難勧告は、4月28日15時に解除されました。
一安心ですが、連日30度近い最高気温が続いており、急激な雪解けによる影響が心配されます。
4月24日・25日に参議院会館での自治体議員女性政策研究交流会に出席してきました。
介護保険からこどもと家族のための社会制度まで、幅広い課題について、講演を聞いたり、意見交換をしたり、中身の濃い二日間でした。
全国各地の女性議員の方と交流でき、元気と活力・パワーを吸収して、大変刺激を受けてきました!
70代の大先輩議員の方から、30代の同年代の議員の方まで、地域で奮闘されている様子にやはり元気が出ます!
吉備国際大学大学院社会福祉学研究科教授の高橋睦子さんによる講演(テーマは「 フィンランドの子育てと子育ちー子どもと家族のための社会制度を」)では、市町村レベルが福祉政策の実際の担い手という力強い言葉にしっかりと自治体レベルでの子育て環境の整備を図らなければと焦りも感じました。