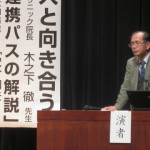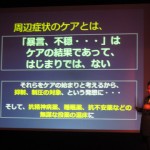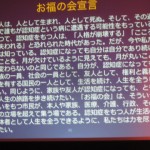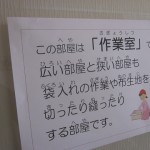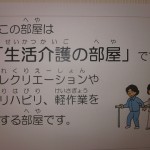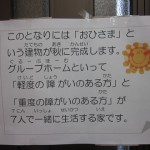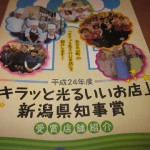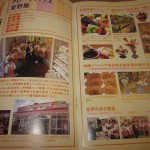3月7日防災会議が開催され、地域防災計画(原子力災害対策編・震災対策編・風水害対策編)について検討しました。
先月募集した「原子力災害対策編」のパブリックコメントは4件。
今後、市のホームページで寄せられたパブリックコメントと意見に対する考え方を公開する予定です。
私は、以下の意見を出しました。
※第1章1節4計画の修正→市は住民の安全を守るもっとも身近な機関として実効性のある計画を策定し、住民の被害を最小限に抑え、住民の安全を守るという観点から常に計画の修正・再検討を図って頂きたい。特に、豪雪地帯である小千谷市の特性、また後述でも要望するが地域説明会等で市内の各地域で出てくるであろう市民の生の声を反映した計画となるようにしていただきたい。
※第1章1節5計画の周知徹底→「必要と思えるものは市民への周知を図る。」という文言が問題だ。防災計画は市民にとって重要な計画であり、必要・不必要の判断は行政の権限で決められるものなのか疑問。また、市民への周知・啓発・協力がなければ38,526人の全小千谷市民の屋内退避・市外退避が整然と行われることは出来ないと考える。事故時だけでなく、日頃からの情報公開・周知徹底は必要不可欠であるとの視点を徹底してもらいたい。
※第1章2節地域の範囲・小千谷市における地域の範囲→小千谷市は市内全域が発電所から半径30キロ圏内ということで、UPZ(避難準備区域)に該当するが、片貝など発電所から20キロ地点は、風速5mの気象条件で約1時間程度で放射性物質が届いてしまう。情報伝達が行われる前に、高濃度の被曝にさらされる事態が予測される。地理的条件に合わせた実効性のある計画を策定してほしい。
※第2章4節2情報の分析整理→住民への情報提供体制の整備を項目に追加してほしい。また、風向きなどで放射性物質の移動や拡散は異なると予想され、当市においても風向きによっては避難方向も異なることから、モニタリングポストを東西南北に設置するなど放射線監視体制の強化を図り、ホームページ上や市庁舎モニター等で監視データを常時公開するなどし、情報分析を図り、市民への情報提供も常に行ってほしい。
※第2章5節緊急事態応急体制の整備8広域的な応援協力体制の拡充・強化→市町村の区域を超えるだけではなく、都道府県を超える広域的な取り組みも明記すべきと考える。
※第2章6節屋内退避、避難体制の整備→小千谷市がUPZに該当するということで、屋内退避が基本となっているが、線量基準が示されていない。距離が発電所から半径30キロだから、屋内退避で十分というのでは、福島原発事故の教訓が生かされていないのではないか。線量基準で、屋内退避となるのか、市外避難となるのか判断すべき。また国の避難指示区域の指定等を待つことが有効なのか。最新の報道では、ベント開放前に放射性物質が拡散していたとする福島原発事故を考えても、小千谷市が屋内退避で被害を免れられるのか疑問であるが、あくまでも屋内退避を基本とするのであれば、情報収集や市民への伝達の拠点となる市役所の建物自体が、放射線防護が可能となるような防災拠点となるべく整備すべき。また、各町内や学校等の建物についても、外気の浸入を防ぐような整備をし、外気と遮断した屋内退避生活ができるような備品の備蓄・配置・整備をすべき。また、風向きなどの状況を見つつ、妊婦や乳幼児、子どものいる家庭を優先的に市外避難させるなどの取り組みが必要ではないか。
※第2章6節3安定ヨウ素剤の配備→迅速に住民へ配布するためにも、屋内退避場所となるような各町内集会所や学校、福祉施設、公共施設などに事前に備蓄・配置しておくべきと考える。
※第2章6節4避難誘導、移動手段の確保→自家用車避難を前提とすることだが、季節ごとの避難経路や避難場所、渋滞対策などをマニュアルや行動計画では盛り込むべき。特に、豪雪地帯である小千谷の特性を考慮した行動計画が必要。また自家用車を持たない方の避難移動手段をどう確保するのか、名簿の作成とともに、災害時の時間帯は昼夜をしれないので、家族単位や地域単位、職場単位、学校単位でのどのような避難・移動が予測されるのか、時間帯ごとのマニュアル、行動計画を作成すべき。また避難状況の確認をどう行うのか、名簿の活用や市⇔市民(町内会・学校・福祉施設・病院・事業所含む)双方の連絡・確認手段がとれるような、分るような仕組み作りを確立すべき。
※第2章6節5災害時要援護者→今後、整備するとのことだが、具体的な交通手段の確保を含めて避難体制の確立を図るべき。屋内退避の場合、市外避難の場合とそれぞれのマニュアル、行動計画が必要。また福祉施設、病院等に関しては、広域での病院間・施設間の協力協定のようなものがそれぞれ必要かと考える。中越地震の場合も市内での受け入れは不可能であり、市外・広域で受け入れていただいた教訓がある。また、災害時要援者の方が、屋内退避となるであろう避難場所(自宅・病院・施設内での屋内退避であろうとも)で、外部と遮断された空間での生活を強いられることは、様々な負荷をかけることになり、一刻も早い広域避難が必要と考える。全市民一斉での屋内退避、市外避難ではなく、線量を基準とした、また風向きなどによる放射性物質の拡散をきちんと情報収集しながら、災害時要援護者はすばやく、優先的に市外避難をさせるべきと考える。また、渋滞などで車内に長時間いなければならないケース等は要援護者には更に負荷をかけることになる。
※第2章6節6学校等→時間帯によるマニュアルや行動計画が必要。(登下校時、校内活動中、校外活動中など)
※第2章6節10屋内退避、避難等の周知→東海村臨界事故、福島原発事故、また中越沖地震の際の柏崎刈羽原発の3~4号機が地震翌日の朝まで冷却出来ていなかったことなど、国、行政からの情報が地元自治体、周辺自治体に一切なかったということが市民・国民側には逆に教訓として根強い。福島原発事故における避難の状況をきちんと教訓として、情報の周知徹底を図るべき。また、「住民に提供すべき情報について整理しておく。」との文言は誤解を与えやすい。この文言にあるような住民に提供すべき情報と提供すべきではない情報の意味はなにか。
※第2章12節3災害時要援護者支援に関する普及知識→高齢者・障がい者・外国人、乳幼児及び妊産婦、また男女の視点などに配慮する防災知識の普及と啓発を行うに際して、十分に、当事者の声を聞く、拾う仕組みを整備してほしい。
※第3章4節2屋内退避、避難等の指標→国や県の指示待ちではなく、最低限の情報しかなかったとしても、気象条件やSPEEDIなども活用した実効性のある予測が市として察知できるような仕組みが必要と考える。
※第3章4節3モニタリングデータの把握→上記第3章4節2屋内退避、避難等の指標とも関連するが、速やかに緊急時モニタリング結果を市民に周知する具体的な方法、また災害時だけでなく、常時モニタリング結果が市民の目に触れるところに周知できるよう方法を確立してほしい。
※第3章4節4指示体系→国・県からの指示がない場合、市長が屋内退避・避難指示を行えることを文言通り、確保してほしい。
※第3章4節9避難地域の決定、避難誘導等→県が行うとされていますが、小千谷市の場合は、防災協定やスクラム支援会議などの実践もあり、他の市町村と広域的な協定の締結を図るべく、協議を進めるべきではないか。防災グリーンツーリズムの観点からも首都圏・関東甲信越だけでなく、近畿・西日本地域なども視野に入れるべきではないか。
※第3章4節12災害時要援護者の避難支援→自主防災組織が基幹避難所へ在宅要援護者を避難させるという支援方法だが、町内会・自主防災組織で、役員のみの対応は無理と考える。地域住民の方、どなたが在宅要援護者を担当するのかも含めた日頃からの役割分担が必要。時間帯や複数での体制等、考慮すべきことは多く、全市一斉の総合訓練ではなく、町内ごとの単発の訓練も必要。
※第3章8節住民等への的確な情報伝達活動→中越大震災の経験も踏まえて、通信網の機能不全や道路網の崩壊などの状況の中で、どう情報伝達を行うのか、聴覚障がい者や視覚障がい者といった災害時要援護者も含めた情報伝達方法を当事者である住民の声を聞きながら確立してほしい。
※全体について① 防災計画に関して、今後、市民への周知・啓発活動ともに、具体的な行動計画やマニュアルの策定にうつると思いますが、その際には、当事者である市民の声を広く聞く、拾うためにも、各町内、集落ごとの説明会や意見を聞く会を開いてほしい。また、商工団体、障がい者団体、女性や子育てサークル、教育、福祉、医療事業所ごとの説明会や意見を聞く会も必要と考えます。中越地震を経験し、また東日本大震災を教訓に、小千谷市民として、災害は時間帯を選ばない、またいかに広域災害が市民生活を直撃するか、特に災害時要援護者に大きな負荷をかけるかを実体験しているわけですから、より具体的な行動計画、マニュアルの策定を図る必要があると考えます。
※全体について② 福島原発事故前の原子力安全委員会の「防災指針」では、10〜50ミリシーベルトの放射線を受ける可能性がある場合には「屋内退避」を、50ミリシーベルト以上の場合には「避難」を検討するとしています。しかし、柏崎刈羽原発の放射能拡散シュミレーションでは、7日間で50ミリシーベルトの被ばくを超える地域は半径50キロを超えています。避難受け入れ区域となる発電所から半径50キロ圏が、避難受け入れではなく、避難準備区域となる可能性が大いにあります。そうなれば、発電所から半径30キロ圏内である小千谷市にとって、屋内退避・市外避難での混乱は今防災計画をはるかに超えるものであるだろう事が予測されます。
また、小千谷市の地形を見ても、また市民感情に鑑みても、小千谷市の一部地域でのみの屋内退避、市外退避などありうるわけはなく、屋内退避・市外避難ともに、緊急事態が起これば、小千谷市にとっては、市内全域で生活基盤が崩壊することに他なりません。リスクを取り除くには、柏崎刈羽発電所は廃炉とし、冷却・解体・廃棄物の隔離保管を永年継続すべきと考えます。
◇国際放射線防護委員会(ICRP)は、自然放射線と医療被曝を除く空間放射線量を、年間1ミリシーベルトとしています(毎時0.19マイクロシーベルト)。また、自然界の大地から放出される放射線量は、年間0.38ミリシーベルトとされています(毎時0.04マイクロシーベルト)。よって、国では空間放射線量の基準案が毎時0.23マイクロシーベルトとされています。
また、原子力規制委員会の検討チームは2013年1月21日、原発事故が起きたときに即時に住民を避難させる放射線被曝(ひばく)線量を毎時500マイクロシーベルト(毎時0.5㍉シーベルト)とする基準で合意したとの報道がありました。0.5㍉シーベルトは一般人の年間被ばく線量限度である1㍉シーベルトに2時間で達する高い値であり、大いに戸惑いを覚えます。実際に、屋内退避、市外避難をすべき線量基準は今だ確定には至っていなく、また策定基準が、500マイクロシーベルトといった高線量になるようでは、住民は、みんな基準よりも低い数値で逃げ始めることは想像に難くありません。