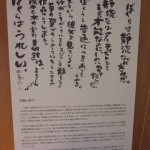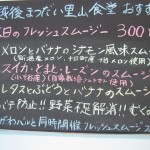9月18日(水)小千谷市議会平成25年第3回定例会の一般質問が行われ、私は、組織改革・人事政策について質問しました。
市長答弁、教育長答弁で、※市職員の人事交流を行う。※教育委員会情報の発信の改善として毎月行われる教育委員会定例会議の傍聴の許可や告知を行う※社会教育委員の公募等を含む教育委員会の様々な改革を検討するなどの成果を得る事が出来ました。
質問の中でも触れましたが、今回質問した項目、組織改革、意識改革、教育委員会の問題点などは、そっくりそのまま「議員」「議会」の課題として当てはまることでもあります。他人事としての上から目線での指摘ではなく、私自身も同じ問題、課題を抱える者として、質問しました。
小千谷市議会のホームページで録画中継が掲載され、答弁等の詳細が確認出来次第、再度、続報で、お知らせします。
(質問内容)
私は、先に通告いたしました要旨に基づき、当市の組織改革・人事政策について質問致します。
近年、超少子高齢化社会の中で、多様化、高度化する市民ニーズに、的確に対応していくことが求められるなど、地方自治体としての小千谷市に市民が期待する責任と役割は大きく、政策形成能力の向上、住民サービス視点、経営的感覚の取得など、市職員に要求されるものは多種多様であります。
こうした要求に対応できる人材を育て生かし、地方行政として市民の期待に応えていくためにも、具体的にどのように組織を変えていくのか、人事政策をどう改革するのか、「組織改革や人事政策」は、持続可能な市民生活の構築に影響を与える重大な事項であると考えることができます。
以下、当市の組織改革・人事政策について伺います。
一点目、人事交流についてでありますが、時代の急激な変化、また行政に対する住民要望が多種多様化する中で、行政が住民ニーズに的確に応えていくためには、人材育成は特に重要であり、人事交流は今後の市の活性化、発展のために必要な案件であると考えます。当市は被災地への職員の派遣は行われておりますが、国、県との人事交流はないのが現状です。
総務省が平成25年1月29日に公表した平成24年8月15日現在の人事交流状況の概要によると、国から自治体への派遣は1,722人、自治体から国への派遣は2,338人と、平成11年からの統計でも年々増加しております。
本県では、部長級以上の役職への出向が、十日町市へ経済産業省・国土交通省から1名ずつ、新潟市・佐渡市へ国土交通省から1名。若手職員の出向では、十日町市が経済産業省、環境省へ。三条市が、経済産業省、国土交通省、新潟市、佐賀県武雄市への派遣等、実績を積んでおります。
県においても、県市町村課が編集、公益財団法人新潟県市町村振興協会が発行している情報誌「NIIGATA市町村情報」等を通じて、市町村との人事交流をアピールしており、情報誌「NIIGATA市町村情報」の過去二年間の近況報告欄では、佐渡市、魚沼市、妙高市、十日町市、出雲崎町、新潟市、新発田市、燕市、阿賀野市、聖籠町などの自治体と県との人事交流の報告が取り上げられております。
自治体職員は総合行政職であり、いずれはその地域の総合企画業務を担う宿命にあります。
また、専門職ではなく、一般事務職として採用されれば、常に同じ分野で同じ部署で定年までの長い年月を過ごすのではなく、市民生活を支える市役所の幅広い業務の中で、異動のたび、まったく異なる業務を経験しなくてはならないと、過酷ではありますが、視野が広がり、大きなやりがいを感じられる職場であると思いますし、市民にとってもそうあってほしいと思います。
このように、他市においても、相互理解の促進、広い視野をもって政策課題に取り組むことができる人材の育成の観点から、国、県、民間団体との人事交流について、積極的に取り組み、実績を重ねておりますが、当市は、人事交流についてどう考えておられるのか、市長の考えをお聞かせ下さい。
また、現在は、人事交流を行っていないにしても、来年度以降の人事交流の予定や見通しはあるのか、お聞かせ下さい。
二点目として、職員の意識改革と政策提案について、4つ伺います。
先日、市職員の公金管理に関する不祥事が発覚しました。
再発防止策としては、チェック態勢などを強化し、再発防止に努めるというのが、この種の不祥事の対策だと考えられますが、モラルの向上、チェック機能の強化などを叫んでも、マニュアルの形骸化などの限界や落とし穴があるかもしれず、組織的な改革の意識付けが大切ではないかと考えます。
改革といっても、イデオロギーや理念を大上段で振りかざすのではなく、そうであれば、福島第一原子力発電所の過酷事故のように「あってはならないことは起きえないこと、ありえないこと、想定外のこと」として、あり得たであろう対策が取れなかった轍を踏むことになりかねません。
これは、行政に限らず、どの組織でも同じだと思うのですが、日常のおかしなことを丁寧に変えていく、直していくことが組織の維持や延命には大切であり、そして、組織として変だなと思ったことを直していく、変えていくこと、その使命・ミッションは誰のためなのか、何の目的のためなのか?を常に振り返り、地方公共団体としては、市民のためであるとの意識付けが重要であると私は、考えます。
小千谷市を代表し統括する執行機関である市長としてのお考えを伺います。
まず、一つ目として、職員の綱紀粛正を平素どのように指導されているのか。今回の職員の不祥事をうけ、どのように指導されていくのか、お聞かせ下さい。
二つ目として、職員不祥事を受け、投書や電話など市民からの反応状況をお聞かせ下さい。
三つ目として、権限のある職務には相当な自己戒律、自己抑制が必要であり、またチェック機能も働かさなければなりません。
しかし、「してはいけないこと」は「してはいけないこと」なんだから、「しない」「起きない」「起こり得ない」ではなく、構造的な問題、組織的な問題、意識的な問題、多角的視点で、防止策を考えなければなりません。
例えば、福祉や介護における身体拘束や虐待の問題があります。身体拘束や虐待は、「あってはならないこと」「起こってはいけないこと」だから、「起こらない」「ありえない」、「起こすな」「やるな」では問題解決できません。加害者になりえる介護職員や家族のモラルが低いから起こるのだ。モラルを向上しろ!施設のいたるところに監視カメラをつけろ!といった主張だけでは、問題発生を防止できないことは多くの方が認識しているところだと思います。
今回の職員の不祥事では、専門職の多い部門など職員の構成や配置・期間等が変化できない組織における問題点を指摘する向きもあります。
専門分野に特化するなど固定化した部署への意識改革や人事方針をお聞かせ下さい。
四つ目として、職員が十分に能力を発揮し,小千谷市発展に貢献できる仕組みを整えることも、職員の意識改革、不祥事防止、メンタルヘルスの向上にもつながると考えます。
当市においても、職員にむけて相当数の研修が行われていますが、この場で提案させていただきたいことは、研修数を増やして、職員の多忙化や負担感を増して、公務員として「公共の利益」の増進のために全力をあげてその職務に取り組む姿勢を、モラルを強制するのではなく、職員による政策提案制度の充実を図るなどの取り組みで、職員のやる気や仕事への充実感を増すことで、意識改革や不祥事防止、メンタルヘルスケアにつなげることも、有効な取り組みの一つではないでしょうか。
また、その取り組みを市民に向けて周知することにより、市民とともに政策を実現する市民協働的な行政の姿勢がより発信できると考えますが、市長の見解をお聞かせ下さい。
三点目として、組織改革として、大きな岐路に立たされている教育行政について、三つ伺います。
今、多くの市民の方が関心のある行政分野の一つとして上げられるのが、教育です。
超少子高齢化社会の中で、「こども」「お子さん」にかける地域、御家族の思いは、大変あついものがあります。
さらに、いじめ、不登校、教師の多忙化など教育現場の抱える様々な課題も指摘さています。
そのような中で、2011年10月の滋賀県大津市のいじめ自殺事件がきっかけとなり、学校などの教育機関をチェック、指導する立場の教育委員会が機能せず、形骸化しているという問題が浮上しています。
こうした背景の中、いじめや体罰などの問題が起こった時の隠ぺい体質を改善するため、自治体トップの権限強化につながるような教育委員会不要論を主張する首長も出ています。
私は、確かに、改革しなければいけないことはありますが、教育委員会は不要とは思いません。教育委員が問題の埒外に置かれない体制が必要と考えます。
一つ目として、本年4月に中教審で教育委員会制度の改革を議論するよう、下村文部科学大臣が指示する等、教育委員会制度の見直しについて、議論が活発化しつつあり、文部科学省が公開している教育委員会に対して指摘されている問題点とその要因として、
教育委員会の意思決定の機会が月1回程度、短時間開かれる会議のみであり、十分な議論がされておらず、適時迅速な意思決定を行うことができない。
教育委員に十分な情報が提供されない。
また教育委員が学校等の所管機関についての情報を得ていない。
教育委員の人選に首長や議会が関心を持たない場合、適材が得られない。
教育委員が職務を遂行する上で地域住民と接する機会が少なく、また委員会の広報活動や会議の公開も十分でない。等が挙げられています。
また、平成24年度小千谷市教育委員会教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価報告書の中でも、学識経験者からの意見等として「教育委員会会議の開催及び審議状況に関する事項について」の中で「臨時代理が多くみられるが、教育委員会での決定を増やすべきではないか」との意見が出されています。
教育長はこのような教育委員会制度改革の問題を当市の教育行政に照らし、どう認識しておられるのか、見解をお聞かせ下さい。
二つ目として、過去の私の一般質問で、教育長、答弁いただいたように、毎月1回行われる教育委員会定例会会議の会議録が、本年4月の会議より、小千谷市ホームページ上で公開されるようになりました。
議事録の公開は、大きなはじめの一歩であると考えますが、まだまだ市民にとっては、教育委員会では何をしているのかわからない、市民の目線で、教育課題に取り組んでいるのか、見えない、遠い存在であると思えます。
市民が可視化できるように、教育委員会情報の発信を改善する必要性があると考えますが、教育長の見解をお聞かせ下さい。
最後に、教育委員会を形骸化させない様々な工夫として、
教育委員会会議の議題についての教育委員を対象として事前勉強会を開催する
教育委員会議では議案の承認にとどまらず委員からの提案に基づき議題を設定する
土日・祝日に開催する
夕方以降の時間帯に開催する
移動(出張)教育委員会を開催する
教育委員会会議の開催日時や議案等の情報をホームペ-ジに掲載するなどして積極的に告知する
教育委員、社会教育委員を公募する等が行われています。
他市町村で取り組まれている教育委員会会議の運営の工夫を当市でも取り入れる考えはないのかお聞かせ下さい。
以上で、質問を終わりますが、答弁のいかんにより、再質問させていただきます。また、今回質問させていただきました項目、組織改革、意識改革、教育委員会の問題点など、そっくりそのまま「議員」「議会」に当てはまることだとも認識しております。他人事としての上からの指摘ではなく、私自身も同じ問題、課題を抱える者として、議論させていただければと思います。
市長、教育長の明解な答弁を期待しております。